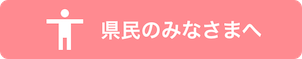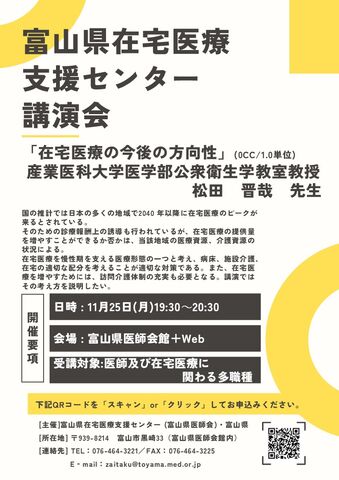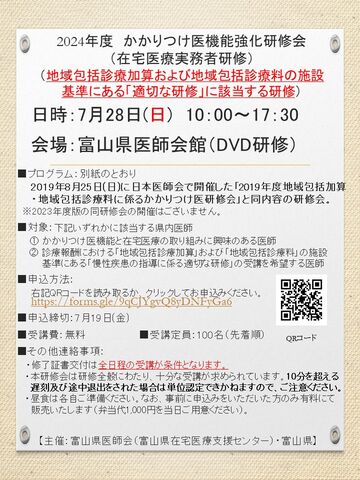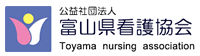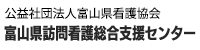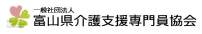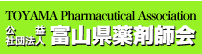- 日時 2025/02/17
- 場所 小矢部市
- 対象 医師・医療介護関係者
人口約2.8万人、高齢化率35%の小矢部市。二次医療圏は砺波ですが、患者は高岡方面に向かうことも多いです。内灘に通う方もおり、がん治療が必要な場合には、富山大学や金沢大学に行くことになります。金沢へは山側環状道路の整備によりアクセスが便利になりましたが、石動駅舎の高架化による階段の高さから、電車での通院を諦めた方もいます。開業医は全科を含めて18院あり、これらの医院・病院が休日当番医を担当しています。少し難しい症例に直面した場合、北陸中央病院がすぐに診てくれるので心強いです。「丁度よい病院」が重要であることは言うまでもありません。
近年、入院は高度化・短期間化し、外来通院は元気でないと受けられない状況となっています。入院と外来に関連した在宅医療がますます身近になりつつあります。特に、在宅専門医が夜間にクリニックに不在でも、在宅医療の方針を立てることが医療文化の一つの転換を示しています。医師に求められる役割は、「いつでも診てくれ、頼れる存在」から、「方針や見通しを立てて支えてくれる存在」へと変化しました。
小矢部市では、開業医同士で不在時の副主治医制「メルヘン在宅安心ネットワーク」を作りましたが、実際には一度も機能しませんでした。患者側も、知らない医師に診てもらうことに抵抗を感じる場合が多く、在宅専門医でない開業医でも十分に見通しを立てていたため、他の医師に頼むことに躊躇したのかもしれません。しかし、力強い支えとなったのは訪問看護の誕生でした。患者たちは、次の往診までに亡くなるかもしれないと誠実に告げられ、その瞬間をいつも訪れてくれる看護師やヘルパーと共有することで満足感を得ていました。
「小矢部医師会訪問看護ステーション」は、平成25年に恐るおそる立ち上げられ、現在では在宅医療に欠かせない存在となっています。その後、他の訪問看護ステーションも相次いで加わり、小矢部市外からの支援も受けながら、特にコロナ後の入院離れの影響で需要が増加しています。連携ツールのICTとしては、メディカルヘルスケアステーションを採用していますが、お互いにラインで連絡することも多くなっています。個人宅だけでなく、在宅対応の施設も増えており、施設ごとの方針に応じて、医師がどの程度イニシアチブを取るか、決断の責任がどこにあるのか、どこまで医療を提供すべきかについて悩む場面もあります。医療知識が限られたケアマネージャーが決定を過度に行ってしまうことへの不満もあり、こうした悩みを共有する場として、平成24年に立ち上げられた「多職種合同事例会議」があります。この研修会は年に4回、「在宅医療推進連絡会」や「小矢部市在宅医療支援センター」が企画し、各会でテーマを設定して話題提供を受け、グループワークを行っています。相手の専門性を尊重し、非難しないという原則を掲げ、行政がファシリテーションを支えています。地方に多く見られる脊髄小脳変性症の在宅支援や胃瘻に関する実際の悩み解決、歯科や認認介護に関する問題など、多職種が率直に疑問や要望を共有し、普段接することのない仕事についての情報交換が行われています。常に約50人前後が参加し、非常に好評を得ています。
【原稿執筆:渡辺 多恵 先生(小矢部市医師会副会長)】